保育士を支援する制度にはどんなものがある?
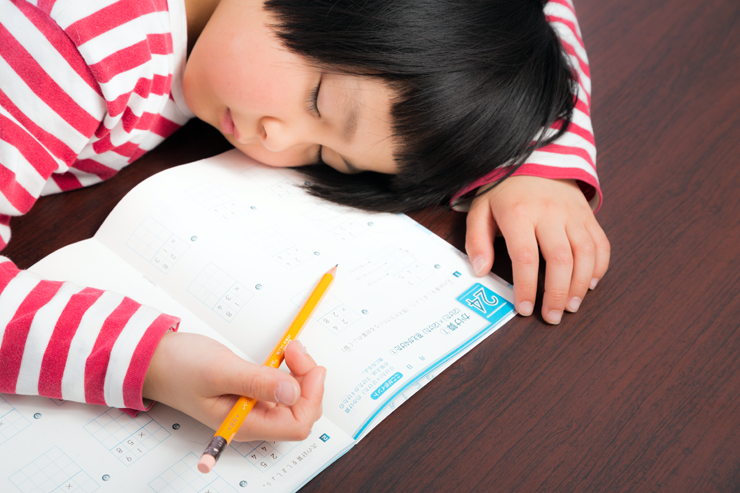
思うように家計収入が増えないなどの理由で共働きをする世帯も少なくないため、子供を預けて働きたい方も多くいるようです。そのため、待機児童解消とともに保育士の確保も重要な課題となっています。保育士不足を解消するために、保育士の資格を持っていながら働いていない人に復帰してもらう制度や保育士の待遇改善のための補助金制度、さらには簡単な研修で子育ての仕事に携わることができる新制度もスタートしています。そこで、これらの各種保育士支援制度についてご紹介します。
☆保育士復帰を促す潜在保育士復職支援プロジェクトとは?
保育士を確保するためには、新しく保育士を育成する方法もありますが、既に資格を持っていて保育の仕事をしていない人に復帰してもらう方法も有効です。そのために用意された制度が潜在保育士復職支援プロジェクトです。制度の狙いは、保育士の資格を保有していて以前は保育士として働いていたが、結婚や出産のために退職していたブランクを心配して復帰できないでいる人や、資格を取得した後に他の仕事に就いたため、保育士の仕事に不安がある人の復帰をサポートすることです。サポートプログラムの内容は地域によって多少の差があるようですが、講義と実習が組み合わさったカリキュラムになっています。最新の保育事情や新保育所保育指針などの情報を講義で得られますので、ブランクが長い人にとっては心強いでしょう。コミュニケーションや遊び方などの講義もあります。実習では遊びや読み聞かせなどを実施することになっています。また、保護者対応についての研修を行っている自治体もあるようです。
☆保育士を支援する補助金制度にはどんなものがあるか?
毎年多くの人が保育士の資格を取得し現場に入っていきますが、保育士を取り巻く環境は厳しく、仕事の厳しさや収入の少なさなどが原因で、新しく入ってきた人の数よりも多くの人が離職している状況になっています。そのため、保育士育成のための補助金制度を整備し、政策的に保育士の育成と職場定着を後押しするようになってきています。例えば東京都では、保育士1人あたり月額約2万円の補助金を出し始めていて、国の補助金である約1万円と合わせると、補助金によって収入が約3万円増える状況になっています(1)。また、横浜市(2)や世田谷区(3)などでは、保育所が借り上げた保育士用の社宅についての家賃補助を行うことによって、保育士を経済的に支える政策も実施されています。ただし、自治体によって財政状況が違うことや待機児童や保育士不足の状況に違いがあるため、補助金制度は自治体ごとに大きく違います。自分が働こうとしている地域ではどんな補助金制度があるのかについて、事前に調べてから就職することをおすすめします。
出典:
(1)東京都福祉保健局、http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jigyo/kyaria-hoiku.html
(2)横浜市、http://www.city.yokohama.lg.jp/kodomo/kinkyu/shikaku.html
(3)世田谷区、http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/103/129/1810/d00137611.html
☆研修を受けるだけで保育の仕事ができる!子育て指導員とは?
保育士不足を解消するために行われている対策は、潜在保育士復職支援プロジェクトや補助金制度だけではありません。新たな子育ての担い手を増やそうと考えられた子育て指導員もその対策の1つです。子育て指導員は、研修を終了することで認定される新しい資格です。保育士になるためには、一定の学校に通うなどの長期間の勉強が必要になりますが、子育て指導員になるには一定の研修を受けるだけで済みますので、保育士の資格を取得するのは難しいが子育て経験を活かして働きたいという主婦などの受け皿になると期待されています。地域によって多少差があるようですが、研修に必要な時間は、共通研修が約10時間、その他専門研修が約10時間から約15時間、合計20時間から25時間程度といわれています。これまでも似たような制度はあったものの、ボランティアという形態をとっていたため報酬はありませんでしたが、子育て指導員の場合は収入も得られます。

